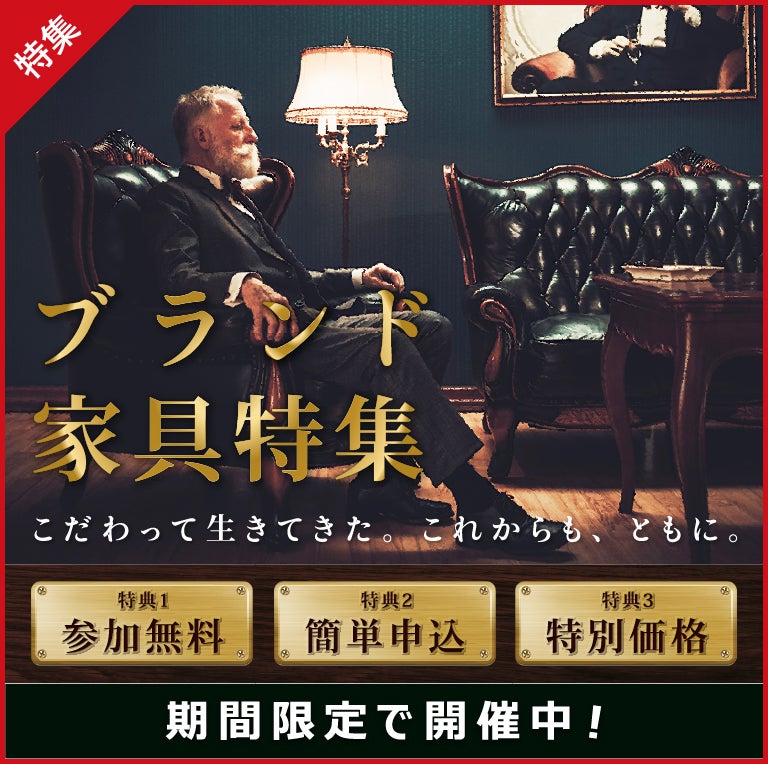お部屋の配色方法や家具・インテリアの選び方を徹底解説!カラーコーディネート講座
お部屋の色のバランスがとれていると、狭いお部屋が広く感じられるようになったり、日当たりのよくないお部屋が明るく感じられるようになったりします。たとえば生活感がどうしても出てしまうキッチンでも、色に統一感があればものが多くても雑然とした印象が軽減されたりします。ここでは、プロじゃなくてもすぐに真似できる、インテリアのカラーバランスを考えるためのヒントをご紹介します。
まず、【ベースカラー】【テーマカラー】【アクセントカラー】の3つの色を決めて、統一感のあるお部屋づくりについて考えてみましょう。リビングルームを例に挙げてみます。
まず、【ベースカラー】【テーマカラー】【アクセントカラー】の3つの色を決めて、統一感のあるお部屋づくりについて考えてみましょう。リビングルームを例に挙げてみます。
ベースカラー
《面積に対しての配色目安:部屋全体の70%》 =床、壁、天井、建具など
ベースカラーはインテリアで大きなスペースを占める部分。ベースとなる色の配分によって、部屋の印象が大きく左右されます。このベースカラー、日本の住宅では白(白を基調にしたアイボリー、ベージュ系も含む)、ライトブラウン色、ダークブラウン色の3色が使われることが多いようです。この3色は、どんなインテリア空間にも合うベーシックなカラーです。たった3色だけなのですが、その配分の違いだけで、部屋のイメージは大きく変わってきます。
| 【白が多い場合 →明るくさわやかな空間】 |
 |
| 【ライトブラウン色が多い場合 →温もりあるやわらかな空間】 |
 |
| 【ダークブラウン色が多い場合 →落ち着きがあってくつろげる空間】 |
 |
テーマカラー
《面積に対しての配色目安:部屋全体の25%》 =カーテン、ソファ、キャビネット、テーブルなど
次に、テーマカラー。ここでの色選びが成功への分かれ道になります。

【統一感ある部屋にしたい】

床の色と同色のキャビネット、テーブルなどを選ぶと統一された印象になります。またソファやカーテンもベースカラーのいずれかの同系色を選ぶと◎
【強い色調の色を使いたい】

例えば、ソファでビビットな赤を使いたい場合は、カーテンなどはできる限り、壁と近い色を選ぶことが無難。大きいサイズの家具に強い色調の色を取り入れる場合は、1アイテムだけに使うことで、アクセントとなり引き立ちます。
【部屋をすこしでも広く見せたい】
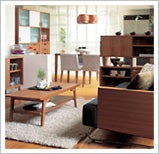
自分の身長より高さのある家具やカーテンは、白などの薄い色を選ぶことで圧迫感を感じにくくなります。また、濃い色のフローリングの場合は、アイボリー系のラグを部分的に敷くと、広々と感じさせる効果があります。
【床の色と違う色の家具を置きたい】

ダークブラウン色にライトブラウン色(ナチュラル色)を合わせてみると、快活に、その逆はダークブラウン色の重さを緩和してくれます。こげ茶の重厚さ、ナチュラル色の軽快さ、両方のよさを取り入れた空間の指し色には、どちらとも相性の良いイエロー系の色が相性◎
【たくさんの色を取り入れたい】

センスよく多くの色を取り入れるには、トーンを合わせることがまとまりの秘訣。トーンというのは、色の調子のことです。ただやみくもに何色も使ってしまうと、たいていはまとまりない印象のお部屋になってしまいますよね。赤、青、緑でも淡い赤、淡い青、淡い緑のペールカラー、暗めの赤、暗めの青、暗めの緑のダークカラーといったように、色の調子を合わせることで、多くのカラーを使っていても、部屋全体には統一感が生まれます。
アクセントカラー
《面積に対しての配色目安:部屋全体の5%》=クッション、絵画、インテリア小物など
最後はアクセントカラー。部屋全体の5%位の割合を考えて、自分の好きな色、ベースに溶け込まないメリハリある色選びをクッションやインテリア小物にどうぞ。自分の好みを発揮できる部分でもあり、なんといっても経済的な面も魅力的♪ちょっと合わないかなと思っていた色に挑戦してみても良いのでは。結構しっくり感じたりするのがコーディネートの不思議なところです。一般的にはアクセントカラーは、ベースカラーやテーマカラーの【反対色】【類似色】から選ぶと、バランス良くまとまると言われています。
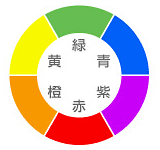
【反対色】
色相環で、ほぼ対角線上に位置するのが反対色です。組み合わせるとお互いの色を引き立たせる効果があります。落ち着きあるイメージや安心感を出したコーディネートにしたい時は、あまり向かないかもしれません。メリハリを効かせたい演出には最適です。【類似色】
色相環で隣り合った色、または近い範囲にある色を指します。黄色~オレンジ、青~紫など、似た色の組み合わせとなるので、合わせやすく、なじみやすい選択かと思います。ただ多用しすぎると、ぼやけた印象になってしまうのでご注意を。